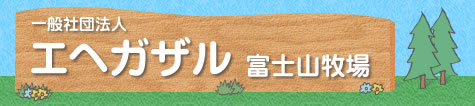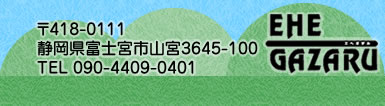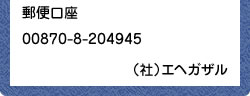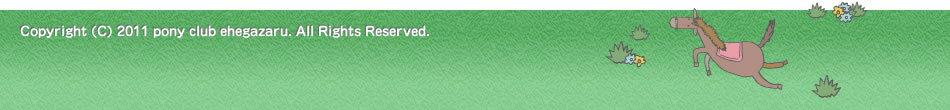局 博一氏(東京大学大学院農学生命科学特任教授)をお迎えして、『馬と人の文化の今後をみつめて』と題して講演会を行いました。
たくさんの方が参加してくださいました。
そもそも馬と人とが関わりはじめて6000年というのには驚きました。
最古のはみ(馬の口につけるもので、その先にタズナがついている)は、BC.4000ということです。
馬介在療法の効果について、心拍数や呼吸数の乗馬前と乗馬中の違いを具体的なデータで見せられ、馬の動きが人間の身体全体の機能に働きかけ、自律神経系に働きかけるという、その効果の大きさ、不思議さに、参加者は熱心に聞き入っていました。
午後には牧場を見ていただき、野あそび会の子どもたちの様子もご覧になられました。
お昼を食べながらの話のなかで、馬のボロは繊維質が多いので土に空気を入れ、しかも未消化の状態なので、土にまかれてから時間をかけて熟成発酵していくので、地力が長持ちするということなどをお聞きしました。
(牛糞はすでに発酵しているものなので即効性はあるが、効きすぎてしまうこともあるという)
みなさん、馬のボロは肥料としてとても効果の期待できるものということです。どうぞエヘガザルのボロをご利用ください。